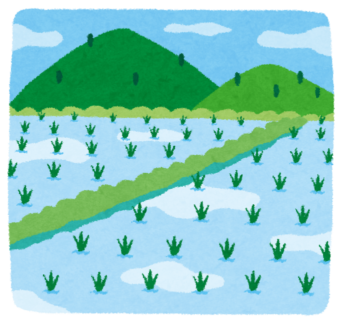あなたが農業とは関係のない仕事を選択して街で生活していて相続で農地を引き継ぐことになったとしたら、あなたは農地の相続に関して何から始めますか。農地の相続手続きは、宅地等の相続手続きとは異なる点があります。この記事は、農地(採草放牧地を含む)を相続したときにする手続き等を説明します。
農地の相続と処分
農地の評価
農地を相続すると農地の相続も相続税の対象となるため、農地の評価方法からこの記事を始めたいと思います。ここでは、国税庁タックスアンサーNo. 4623に基づいて農地の評価方法を説明します。
国税庁は、(1)純農地、(2)中間農地、(3)市街地周辺農地、及び(4)市街地農地の四種類に農地を区分しています。相続した農地がどの区分に該当するのかは、国税庁の評価倍率表を見ることでわかります。評価倍率表において(1)純農地、(2)中間農地、(3)市街地周辺農地、及び(4)市街地農地はそれぞれ純、中、周比準、及び比準又は市比準の略称で記載されています。
純農地及び中間農地の評価
純農地及び中間農地の評価額は、その農地の固定資産税評価額に、評価倍率表に記載されているその農地に対する倍率を乗じて評価します。
市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地の評価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80パーセントに相当する金額によって評価します。
市街地農地の評価
市街地農地の評価額は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積(面積)を乗じて計算します。これを宅地比準方式と呼びます。
宅地であると仮定したその市街地農地の1平方メートル当たりの価額は、その土地が存在する場所の評価が路線価方式で行われているのであれば路線価であり、倍率方式で行われているのであれば固定資産税評価額に倍率を乗じて算出される価額です。
市街地農地が500平方メートルを超える場合ではその農地の評価額は、宅地比準方式で算出された評価額に規模格差補正率を乗じて計算されます。
市街地農地又は市街地周辺農地(市街地農地等と総称します)を相続又は贈与により取得した者は、相続税又は贈与税の申告に際し、相続税又は贈与税の申告書に「市街地農地等の評価明細書」を添付します。
これは、農地が山林又は原野であっても同じです。
相続の届出
あなたが農地を相続したときは、農地の相続登記に加えて農地の相続の届出をしなくてはなりません(農地法第三条の三)。
対象者
農地の相続の届出の対象者は、相続、遺産分割、又は包括遺贈によって農地の権利を取得した者です。特定遺贈によって農地の権利を取得した者は、届出ではなく、農業委員会の許可を必要とします(農地法第三条第一項)。余談ですが、離婚時の財産分与により農地の権利を取得した者も、許可ではなく届出を要します。
届出先
農地の相続の届出の届出先は、その農地が所在する市町村の農業委員会です。各農業委員会の窓口やホームページに届出の様式があります。
相続した農地が土地改良区の受益地である場合、土地改良区の組合員資格得喪通知書を土地改良区に提出します。相続した農地が土地改良区に該当するか否かは、農業委員会に確認してみてください。
相続した土地の地目が農地ではなく森林であった場合、市町村長への事後届出が必要です。実際には相続した土地のある市町村の林業担当課に届け出ます。
期間
農地の相続の届出の期間は、相続発生からおおむね10か月です。
農地や山林の相続時に必要な書類
不動産の相続手続のために登記簿謄本、名寄帳や評価証明書、及び公図を取得することはよく知られていると思います。相続した不動産の中に農地や山林が含まれている場合、これらの書類に加えて役所の資産税課等で地番図を取得しておくとよいでしょう。
農地の相続登記
農地の相続登記は、宅地の相続登記と同様に法務局で行います。農地の相続人は、その相続が発生したことを知った日から3年の間に登記の申請をしなければなりません。
相続後の農地の処分(活用)
相続した農地の活用法としては「①自分で農業をする」、「②他の農業者に農地を貸す」、「③農地を転用する」、及び「④農地を売却する」が考えられます。
農業をする・農地を転用する
①の相続した農地で農業をする場合、農業用水等は他の農業者との共用になっていることもありますので当地の自治体で新規就農に関して相談してみるとよいでしょう。③の農地を宅地や工場用地等に転用する場合には当地の都道府県知事の許可が、4ヘクタール以上の農地を同一の目的のために転用する場合では農林水産大臣の許可が必要になります。許可は、農業委員会を経由して許可を求めて得ます。
③の場合、知事等の許可が必要と書きましたが、相続した農地の性質によって少しずつ手続が異なってきます。相続した農地の転用を目指す場合、まずその農地がどのような農地であるのか把握することが大事です。
農振法と農用地からの適用除外
都道府県知事は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業の振興を図ることが相当であると認める区域を農業振興地域に指定し、指定された地域の区域内に存在する市町村は、その農業振興地域内の農用地等として利用すべき土地の区域(「農用地区域」)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分等を定めることになっています。
農業振興地域内農用地区域内の農地(「農振農用地」又は「青地」と呼ばれます)は、相当の期間にわたって農業利用すべき土地として指定されているため、相続した農地がこの農振農用地である場合、農地転用は原則として認められません。それでも農地転用を試みる場合、農用地からの除外(農振除外)を当地の市町村の農政課等に申請します。農振除外を経たうえで知事等に農地転用の許可を求めます。
農振農用地以外の農地の転用
農業振興地域内農用地区域外の農地(農業振興地域内に存在する農振農用地以外の農地も含む)は、「青地」に対して「白地」と呼ばれます。「白地」は、さらに4種類の農地区分、すなわち、甲種農地、(乙種)第1種農地、(乙種)第2種農地、及び(乙種)第3種農地に分類されます。各種農地は次のような農地です。
| 甲種農地 | (乙種)第1種農地 | (乙種)第2種農地 | (乙種)第3種農地 | |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の実施後8年以内の農地や特に良好な営農条件を備えている農地 | 10 ha以上の規模の集団農地、土地改良事業等の対象となった農地や良好な営農条件を備えている農地 | 市街地化が見込まれる区域内に存在する10 ha未満の農地又は生産性が低い農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
| 農地転用の可否 | 原則転用不可 | 原則転用不可 | 第3種農地に代替となる土地が存在する場合には転用不可 | 原則転用許可 |
ただし、転用とする農地が市街化区域にある場合では農業委員会に転用の届出をします(農地法第四条及び農地法施行令第三条)。
土地改良区からの除外申請
土地改良区とは、農地の有効利用のために農地の整備や農業用水路の工事等を行う団体のことをいいます。「土地改良法」に基づき都道府県知事が認可して設立された土地改良区には対象となる土地と組合員が所属することになります。自分の土地が土地改良事業の対象になっていると農地転用は許可されないため、農地転用を考えている人は自分の農地を土地改良区から除外してもらえるように土地改良区に申請することになります。
土地改良区は、借入金と組合員の賦課金で運営されているため、土地改良区からの除外を求める者は地区除外決済金を支払う必要があります。
農地を貸す・売る場合
②の農地を他の農業者に貸し出す(貸借権を設定する)場合や④の農地を売却する(所有権を移転する)場合には当地の農業委員会の許可が必要になります。農業委員会の許可を得ずに貸借権を設定したり所有権を移転したりしてもその貸借権設定や所有権移転は無効であり、その土地の登記はできません。
農地バンクと農地の貸借・売買
農地の貸借は、市町村が作成する「農用地利用集積計画」に基づいて行われています。農業委員会の許可を受けた農地の貸借権設定に加え、令和7年4月からは農地バンクを介して農地の貸借を行うことができるようになります。
農地バンクとは、「農地中間管理事業の推進に関する法律」に規定される「農地中間管理機構」のことです。市町村とは別に農地バンクも「農用地利用配分計画」を策定していましたが、市町村の「農用地利用集積計画」と一本化して農地バンクが「農用地利用集積等促進計画」を策定することになりました。
それまでの農地の貸借では農地の貸し手と借り手が直接交渉を行う必要がありましたが、令和7年4月からは農地バンクが「農業経営基盤強化促進法」に基づいて貸借契約を媒介することになります。農地バンクが介在することで次のようなメリットが得られるとされています。
- 貸し手のメリット
- 賃料は、農地バンクから振り込まれる(借り手からの賃料振込について心配しなくてよい)
- 貸した農地は、貸付期間満了後に必ず返却される
- 農地バンクに貸し付けた農地について、税制優遇措置が受けられる
- 借り手のメリット
- まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられる
- 複数の所有者から農地を借りる場合であっても診療支払いや契約事務について農地バンクが契約を一本にまとめてくれる
- 貸し手の相続時の対応は、農地バンクが行ってくれる
- 地域のメリット
- 機構集積協力金が支払われる
- 農家負担ゼロという条件の整備が受けられる
さらに、農地の所有者が農地バンクを通じて農地を売却すると、譲渡所得の特別控除等を受けることができます。
まとめ
以上をまとめると次のようになります。
農業委員会や役所の林業担当課への届出書等の作成は行政書士の業務です。農地や森林を相続することになり/なりそうで困っている方は、まず行政書士にご相談ください。