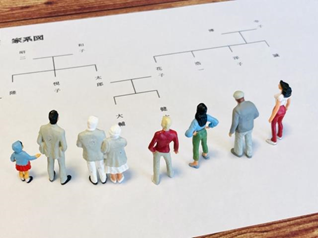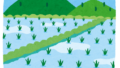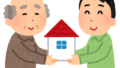相続に関する様々な情報が世の中に溢れており、相続に関心を有する人たちがそれだけ多いことを意味しているのでしょう。このような相続に関する情報には遺産分割に関するものや相続税の節税に関するものがあります。
皆さんの中には「生前贈与を利用して相続税を節税しましょう」等のフレーズを見たことがある人も多いと思います。贈与に関する税制が令和5年に改正され、令和6年1月1日より改正税制が贈与に関して適用されています。これにより、令和9年1月1日以降の相続税について改正税制の影響が現れます。
遺産の配分に失敗すると不満を持つ相続人が現れたり、相続税を払うだけの現金がないのに遺言により不動産を取得する相続人が現れたりします。筆者は、相続税及び贈与税の基礎知識を持っていることは、このようなトラブルを防止するためにも大事だと考えます。
本記事は、国税庁ホームページの記載に基づいて相続税及び贈与税の仕組みを説明するものであり、遺産の配分を考えるときの参考になることを目的としています。本記事は個別具体的に相続税及び贈与税を計算することを目的としたものではないため、正確な税金の額を計算したい方は税理士にご相談ください。
相続財産の評価
相続における遺産分割の手順と同じで被相続人の財産を評価することが最初にする作業です。
相続税の課税財産
相続税の納税義務者と課税財産
表1.納税義務者
- 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した個人
- 被相続人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けた個人
納税義務の範囲は、被相続人及び相続人又は受遺者が日本国内に住所を有しているか否か又は日本国籍を有しているか否かで少しずつ異なってきますが、細かすぎる話のため、ここでは説明しません。本記事は、被相続人及び相続人又は受遺者の双方が日本国内に居住する日本国籍保有者である場合の相続税の課税について説明します。
表2.課税財産
- 本来の課税財産
- みなし相続財産
- 相続開始前7年以内に贈与を受けた暦年課税に係る財産
- 相続時精算課税の適用を受けた財産
「本来の課税財産」は、相続又は遺贈により相続人又は受遺者が取得した財産のことです。「みなし相続財産」は、生命保険金等や退職手当金等、法律的には相続又は遺贈により取得したものではないが、実質的に相続又は遺贈により取得したと言える財産のことです。
相続税の非課税財産
表3.非課税財産
- 墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 一定の公益を目的とする事業を行う者が取得した当該公益事業の用に供する財産
- 相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額
- 相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額
等
生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額は、それぞれ、(500万円×法定相続人の数)の計算式で算出されます。この「法定相続人の数」は、相続放棄をした法定相続人がいたとしても変わりません。
民法では養子は相続人になれますが、相続税法では相続税の計算に算入できる養子の数に制限があります。被相続人に実子がいる場合では相続税の計算に算入できる養子は一人まで、被相続人に実子がいない場合では相続税の計算に算入できる養子は二人までです。ただし、以下の者は実子と同様にみなされます。なお、この養子の制限は、遺産に係る基礎控除額の計算及び相続税総額の計算についても当てはまります。
表4.実子とみなされる養子
- 特別養子縁組により養子となった者
- 配偶者の実子で、被相続人の養子になった者
- 配偶者の特別養子縁組により養子となった者で、被相続人の養子になった者
- 実子等の代襲相続人
相続税の計算では養子の数に制限がありますが、これは遺産分割について相続人となる養子の数に制限があるという意味ではありません。ご注意ください。
債務控除
相続人又は包括受遺者が承継した被相続人の債務の金額は、取得財産の総額から控除されます。控除が認められる債務には次のものがあります。
表5.控除が認められる債務
- 相続人又は包括受遺者が承継した債務
- 被相続人の債務で相続発生の際現に存在する債務(公租公課等)
- 確実と認められる債務
「確実と認められる債務」とは「確実と認められない債務」ではない債務であり、例えば、保証債務が「確実と認められない債務」に相当します。債務者の借金の保証人としての被相続人の立場を承継した者が借金を債務者の代わりに支払っても後で債務者から支払った金額を返却される可能性があるため、保証債務は確実と認められない債務なのです。
債務とは異なりますが、被相続人の葬式の費用を被相続人の財産の中から支払った場合、相続人又は包括受遺者が取得した財産の価額からその葬式の費用を控除することができます。ただし、葬式の費用のうち、控除することができない費用(香典返しの費用等)もあるので注意が必要です。
相続財産の評価
相続財産の中には預貯金以外にも証券及び自動車などの動産並びに不動産のような物もあります。相続税の税額を計算するためにはこれらの物に価額を付ける必要があります。これらの物の価額は、被相続人がこれらの物を取得したときの価額(取得価額)ではなく、相続が発生したときの時価によります。
土地の評価
土地の評価は、宅地、田、及び山林などの地目別に判断されます。さらに、土地の評価は、土地の上にある権利によっても変わってきます。例えば、宅地が借地である場合、その土地の相続税評価額は(自用地価額×借地権割合)の計算式で算出されます。このような例を以下にまとめます。
| 内容 | 評価額 |
|---|---|
| 宅地が借地である | 自用地価額×借地権割合 |
| 宅地を貸している | 自用地価額-自用地価額×借地権割合 |
| 宅地の上に貸家を立ててその貸家を貸している | 自用地価額-自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合 |
評価の方式
土地の評価には路線価方式と倍率方式があります。路線価方式によって評価することとされている地域内にある宅地は路線価方式で評価されます。
路線価が定められていない地域の土地は倍率方式で評価されます。倍率方式は、評価する土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式です。固定資産税評価額は、市役所や町村役場で確認できるほか、固定資産税の納税通知書にも記載されています。倍率は、国税庁ホームページ内の評価倍率表で確認できます。
宅地が路線価方式で評価される場合、その宅地が二本以上の道路に接している等の特徴によって評価額が変わってきます。正確な土地評価額を知るためには土地家屋調査士や相続を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。
市街地には路線価が定められているため、農地が市街地又は市街地の周辺に存在する場合ではその農地の評価方法が複雑です。正確な土地評価額を知るためには専門家に相談するとよいでしょう。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)
被相続人等の居住の用又は事業の用に供されていた宅地等については一定の要件を満たす場合に相続税の課税価格から一定の額を減ずることができます。ただし、この特例は以下の宅地等には適用できません。
- 相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等
- 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等
- 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等
小規模宅地等の特例を適用することができる宅地等には以下のものがあります。
特定居住用宅地等
相続開始の直前において
区分1.被相続人の居住の用に供されていた宅地等
区分2.被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等
特例の適用を受ける取得者の要件
| 区分 | 取得者 | 取得者等ごとの要件 |
|---|---|---|
| 1-1 | 被相続人の配偶者 | 要件なし |
| 1-2 | 被相続人の居住の用に使用されていた一棟の建物に居住していた親族(子など) | 相続開始の直前から申告期限までその住居に居住し、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している |
| 1-3 | 1-1及び1-2以外の親族 | (以下の全ての要件を満たすこと) (イ)被相続人に配偶者や同居の親族がいない (ロ)宅地を相続した親族は、相続開始の3年前までに国内にある「自分又は自分の配偶者」、「3親等以内の親族」、又は「自分と特別な関係にある特定の法人」が所有する家屋に居住したことがない (ハ)その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで保有している (ニ)相続開始時に居住している家屋を過去に保有していたことがない |
| 2-1 | 被相続人の配偶者 | 要件なし |
| 2-2 | 被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限までその住居に居住し、その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 330 m2 | 80% |
特にケース1-3の特例を、被相続人と同居していなくても使用できる小規模宅地等の特例ということから、業界では「家なき子特例」と呼びます。
特定事業用宅地等
相続開始の直前において
区分1.被相続人の事業の用に供されていた宅地等
区分2.被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等
特定事業は、貸付事業以外の事業になります。
特例の適用を受ける取得者の要件
| 区分 | 事業継続要件 | 保有継続要件 |
|---|---|---|
| 1 | その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その申告期限までその事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
| 2 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 400 m2 | 80% |
相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は、原則として特定事業用宅地等に該当しませんが、例外的に特定事業用宅地等に該当する場合もあります。
特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前において、被相続人及び被相続人の親族等が法人の50%超の発行済株式を有しているか出資をしているその法人の事業の用に供されていた宅地等
特定同族会社事業は、貸付事業以外の事業になります。
特例の適用を受ける取得者の要件
| 法人役員要件 | 保有継続要件 |
|---|---|
| 相続税の申告期限においてその法人の役員である | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 400 m2 | 80% |
貸付事業用宅地等
相続開始の直前において
区分1.被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
区分2.被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
特例の適用を受ける取得者の要件
| 区分 | 事業継続要件 | 保有継続要件 |
|---|---|---|
| 1 | その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その申告期限までその貸付事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
| 2 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 200 m2 | 50% |
相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として貸付事業用宅地等に該当しませんが、例外的に貸付事業用宅地等に該当する場合もあります。
それぞれの小規模宅地等について、要件を満たしており、かつ、取得することになった宅地等の面積が限度面積を超えている場合、その限度面積について課税価格が表示の割合で減額されます。
特定居住用宅地と特定(同族会社)事業用宅地等を同時に取得することになった場合でも双方について課税価格が減額されますが、貸付事業用宅地等と他の種類の小規模宅地等を同時に取得することになった場合では宅地等の面積について制限があります。
家屋の評価
家屋の価額は、1棟ごとに、その家屋の固定資産税評価額により評価します。貸家の価額は、その家屋の固定資産税評価額を基に借家権割合と賃貸割合から計算します。その計算式は、(固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)になります。
株式の評価
上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する次のAからDの価額のうちの最低の価額になります。
- 被相続人が死亡した日(課税時期)の最終価格(終値)
- 課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
株式が2以上の金融商品取引所に上場されている場合では納税義務者が金融商品取引所を選択します。
非上場株式の評価
金融商品取引所に上場されていない株式の評価は、税理士に依頼されるとよいでしょう。ここでは非上場株式の原則的評価方式の概略を説明します。
まず、対象となる株式を発行している会社をその総資本価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社、及び小会社のいずれかに分類します。
大会社に分類された会社の非上場株式の評価額は、類似業種の株価を参照してその会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」、及び「純資産価額」で比準して決定されます。これを類似会社比準方式といいます。
小会社に分類された会社の非上場株式の評価額は、「相続税評価額により計算した会社の総資産価額」より相続税評価額により計算した負債の額」及び「評価差額に対する法人税額等相当額」を差し引いた残額を課税時期における発行済み株式数で除して決定されます。これを純資産価額方式といいます。
中会社に分類された会社の非上場株式の評価額は、大会社の類似会社比準方式と小会社の純資産価額方式を併用することにより決定されます。
公社債の評価
債券には利付債と割引債がありますが、どちらも課税時期におけるその債権の価額が評価額になります。個人向け国債の場合では、その国債の額面金額に経過利子相当額を加算し、そこから中途換金調整額を差し引いた残額がその国債の評価額になります。
自動車の評価
被相続人が所有していた自動車の評価額は、①その自動車の市場における買取価格、②その自動車の買取業者による査定額、③実際の売却代金額、又は④減価償却により計算した価額になります。実際には①か②の価額が用いられるようです。
課税遺産総額の計算
まず、遺産分割協議又は遺言により各相続人が被相続人から承継することになった表2の①本来の課税財産の価額、②みなし相続財産の価額、③相続開始前7年以内に贈与を受けた暦年課税に係る財産の価額、及び④相続時精算課税の適用を受けた財産の価額の総額を計算します。この総額から非課税財産の価額、控除が認められる債務の価額、及び葬式費用を差し引いて正味の遺産額を求めます。この正味の遺産額から基礎控除額を減算して「課税遺産総額」を求めます。
基礎控除額は、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算式で算出されます。法定相続人の中に相続放棄した者がいたとしても基礎控除額の計算では相続放棄がなかったものとします。
相続した金融財産等の価額が基礎控除額以内であったとしても相続税の申告を行ったほうがよいと言われています。