前号の記事では遺言で行うことのメリットとデメリット、及び各遺言方式のメリットとデメリットを説明しました。今号の記事は、被相続人が、例えば、相続人以外の者に財産を遺したい場合に採る手続きである遺贈、及び相続人のために確保されるべきである相続財産の割合を意味する遺留分について説明します。
相続人以外に財産を遺す遺贈
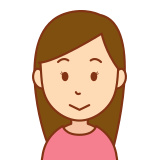
祖母から遺贈を受けました。遺贈された財産には贈与税が課されるのでしょうか?それとも相続税でしょうか?
遺贈とは、遺言する者(遺言者)が遺言により他人に自分の財産の一部又は全部を贈与することをいいます。遺言者は、遺言の中で当然に自己の財産の分割について指定をすることができますが、同じ遺言書の中で相続人に対する指定と相続人以外の者(受遺者)に対する指定をすることができます。例えば、孫に財産の一部を与えたい場合、その孫が代襲相続人でなければ、遺贈することになります(代襲相続人であれば相続になる)。また、特別寄与者に財産の一部を与える場合も遺贈を用いることになります。
ただし、遺贈には注意するポイントもあります。まず、遺贈すると遺贈財産に相続税が加算される場合があります。また、遺贈という形での譲渡された財産の中に不動産がある場合、その不動産に対して相続税に加えて登録免許税及び不動産取得税も課税されます。この不動産を相続により受け継いだ相続人と遺贈により受け継いだ相続人以外との間では登録免許税の税率が異なりますし、下で説明する特定遺贈により不動産を受け継いだ場合ではその不動産に不動産取得税がかかります。節税を考えている方は遺言書の作成前に税理士と相談することをお勧めします。
遺贈の方式としては具体的な財産名を挙げて遺贈する「特定遺贈」、及び具体的な割合を挙げて遺贈する「包括遺贈」が挙げられます。「包括遺贈」の受遺者は、相続が発生したら相続人と共に遺産分割について協議しなくてはなりませんし、負の財産を引き受ける可能性もあります。そのため、包括遺贈の受遺者は相続人と同様に遺贈を承認・放棄する権利を有します。
遺贈の放棄
包括遺贈の放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。「特定遺贈」の受遺者も同様に遺贈の承認・放棄する権利を有していますが、相続人及び包括遺贈の受遺者と異なり、特定遺贈の放棄は、家庭裁判所を介することを要せず、遺言執行者又は他の相続人に意思表示して行います。
遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書に記載されていない被相続人の財産があっても遺言書は有効です。遺言書に記載されていない被相続人の財産は、遺産分割協議を経て分割されることになります。
各相続人の遺留分に気を付ける
以前の記事において各相続人の法定相続分について説明しました。遺産分割協議や遺言の中で自己の相続分が法定相続分に満たないことについて不満がある相続人は、どのようなことができるでしょうか。そのために用意されている制度が「遺留分」の制度です。遺留分について自己の権利を使用するか使用しないかは、各相続人の選択に任されています。
遺留分権利者
遺留分権利者は、被相続人の①配偶者、②子とその代襲相続人、及び③直系尊属(「被相続人」の親、祖父母)です。被相続人の兄弟姉妹、すなわち傍系は遺留分権利者から除外されていますが、その代わりに被相続人の兄弟姉妹を相続人から廃除することができないようになっています。
遺留分の割合
各相続人の遺留分の割合(個別的遺留分)は、総体的遺留分と各相続人の相続分の割合から決定されます。総体的遺留分は、①直系尊属のみが相続人である場合の1/3と②それ以外の場合の1/2の二通りがあります。個別的遺留分は、これらの割合に各相続人の相続分の割合を乗じることで決まります。例えば、配偶者と直系尊属が共同相続人である場合、配偶者の個別的遺留分は1/2×2/3=1/3であり、直系尊属の個別的遺留分は1/2×1/3=1/6になります。配偶者と子が共同相続人である場合、配偶者の個別的遺留分は1/2×1/2=1/4であり、子の個別的遺留分も1/2×1/2=1/4になりますが、子が複数いる場合、子一人当たりの個別的遺留分は1/4を子の人数で除算した値になります。
遺留分額の算定
遺留分額は、被相続人の基礎財産の価額に上で決定した個別的遺留分の割合を乗じることで算定されます。この「被相続人の基礎財産」は、相続額の算定と同じように、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に被相続人が贈与した財産の価額を加算し、さらに被相続人の債務の額を減算したものです。この「贈与財産」については民法に以下のような決まりがあります。
I. 相続開始前の1年間にした贈与を基礎財産に算入する
II. 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、贈与開始1年よりも前にされていても基礎財産に算入する
III. 共同相続人の一人に対してされた贈与が特別受益に該当し、且つ、相続開始前の10年間にされたものであれば基礎財産に算入する
IV. 負担付贈与については贈与財産の価額から負担の価額を控除した額を基礎財産に算入する
V. 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、負担付贈与とみなしてその行為の対価から負担の価額を控除した額を基礎財産に算入する
遺留分侵害額請求
遺留分権者は、自己の遺留分に満たない額が遺言で指定されているか、又は遺産分割協議で決定された場合、遺留分侵害額に相当する金額について遺留分侵害額請求権を有することになります。この遺留分侵害額の算定は、遺留分権者が相続した財産の価額、遺留分権者が遺贈又は贈与により得た財産の価額、及び遺留分権者が承継することになった被相続人の債務の価額を考慮して行います。
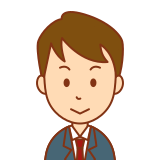
遺留分権者にはもちろん遺留分侵害額請求権がありますが、必ず請求しなければならないというものではありません。
遺留分侵害額請求権の行使は、①相手方に意思表示をして(遺産分割協議とは別の)協議を求め、②協議で解決しない場合は内容証明郵便等で意思表示し、③それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをします。遺留分侵害額請求を認められて得た金銭は、相続財産の中に戻されるものではないため、遺留分侵害額請求の前になされた遺言や遺言分割協議はそのまま有効です。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与若しくは遺贈があったことを知ってから1年、又は相続の開始から10年を経過すると時効で消滅します。
まとめ
今号の記事は、遺贈と遺留分について説明しました。今号のポイントを以下にまとめます。
これまでの記事の内容から、遺言の作成には各相続人の法定相続分、特別受益及び寄与分、並びに遺留分を考慮することが大事であることが理解できます。次号の記事は、遺言者の相続発生後の手続きである「遺言執行」を説明します。



