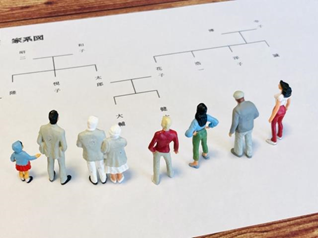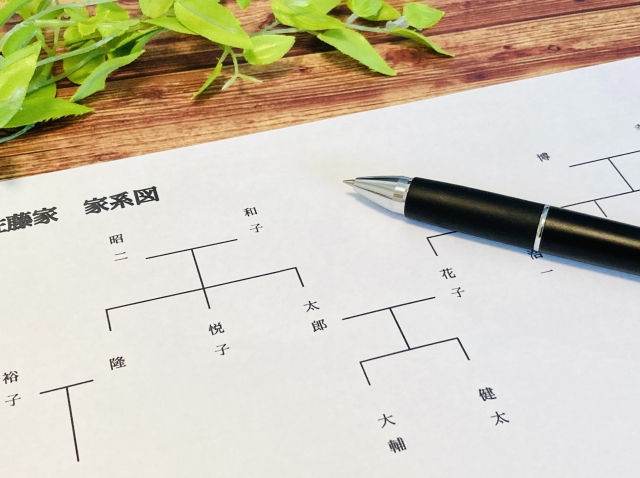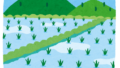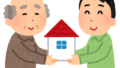相続税の計算
前ページで説明した課税遺産総額を各相続人の法定相続分により按分し、それぞれの金額について以下の表において記載される税率と控除額から各相続人の相続税額を算出します。こうして求めた相続税の総額を求め、各相続人が取得した被相続人の財産の実際の割合をこの総額に乗じて各相続人の相続税額を計算します。
相続税の税率早見表(令和6年4月1日現在)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続人となった者が被相続人から2親等以降である場合(被相続人の兄弟姉妹、甥姪、及び親(被相続人の子)が生存している場合の被相続人の養子にした孫に相当)、その相続人の相続税額は2割加算の対象です。その後、各相続人について税額控除の額を相続税額から控除したり配偶者の税額軽減をしたりして実際に支払うべき相続税額を算出します。
相続税の軽減・控除
各相続人の属性によって各相続人が支払う相続税を軽減できる場合があります。以下にそのような制度を説明します。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税額の軽減は、1億6000万円の配偶者控除と呼ばれることがありますが、正確には軽減です。どういうことか説明します。
この制度は、被相続人の配偶者が支払う相続税を軽減するためのものであり、税額を軽減するための計算式が定められています。その計算式は以下のものです。
(配偶者税額軽減額)=(相続税の総額)×(①と②のうちの少ない方)/(課税遺産総額)
①:配偶者の法定相続分に相当する額(1億6000万円未満であったら1億6000万円とする)
②:配偶者が実際に取得した額
配偶者が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された軽減額を配偶者の相続税額から差し引いた残額になります。なお、被相続人の配偶者にあたる人物が被相続人と内縁関係であった場合にはこの制度は適用されません。
未成年者控除
被相続人の財産を取得した者が法定相続人であり、かつ、未成年者である場合に未成年者控除が適用されます。本制度は、日本国内に住所を有する未成年者を対象としていますが、その未成年者が日本国内に住所を有していなくても対象になる場合もあります。控除金額は、次の計算式から算出されます。
(未成年者控除額)=10万円×(18歳-その未成年者の年齢)
年数の計算に関し、1年未満の期間は1年に切り上げます。令和4年より成年年齢の変更に伴い計算式中の20歳が18歳になりました。
未成年者が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された金額を未成年者の相続税額から差し引いた残額になります。未成年者の控除額がその未成年者の相続税額よりも大きい場合、未成年控除額とその未成年者の相続税額の差額は、その未成年者の扶養義務者である相続人の相続税額を軽減するために利用可能です。
障害者控除
被相続人の財産を取得した者が法定相続人であり、かつ、85歳未満の障害者である場合に障害者控除が適用されます。本制度は、日本国内に住所を有する障害者を対象としています。控除金額は、次の計算式から算出されます。
(障害者控除額)=10万円×(85歳-その障害者の年齢)
年数の計算に関し、1年未満の期間は1年に切り上げます。
85歳未満の障害者が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された金額を障害者の相続税額から差し引いた残額になります。障害の等級が1級である特別障害者の場合では計算式中の10万円が20万円になります。
相次相続控除
相次相続控除は、10年以内に続けて相続が発生した場合に前回の相続で課された相続税額のうちの一定額を新たに発生した相続に係る相続税額から控除する制度です。
次の要件に当てはまる人が相次相続控除の対象者です。
- 被相続人の相続人である
- その相続の開始前10年以内の相続により被相続人が財産を取得している
- その相続の開始前10年以内の相続により被相続人が取得した財産について、被相続人に相続税が課されている
例えば、父親の死亡から10年以内に母親も死亡して母親の相続が発生した場合、父親(母親にとっての夫)の死亡時に母親が父親の遺産を部分的にでも取得して相続税を支払っていたらその両親の子は相次相続控除の対象者です。
各相続人の相次相続控除額は、次の計算式で求められます。
(相次相続控除額)=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
式中、C/(B-A)が100/100を超えるときは100/100とします
A:今回の被相続人が前回の相続で取得した財産に対して課された相続税額
B:今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額
C:今回の相続で相続、遺贈及び相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した全員の純資産価額の合計額
D:相次相続控除の適用を受ける相続人が取得した純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
この計算式における「総資産価額」とは、取得財産と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額から債務および葬式費用の金額を差し引いた金額になります。
各相続人が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された控除額をその相続人の相続税額から差し引いた残額になります。
外国税額控除
外国税額控除とは、海外にある被相続人の相続財産について相続人が外国の法令によって相続税等を課せられた場合にその金額をその相続人の相続税額から控除することです。
暦年課税分の贈与税額控除
相続人になる者が被相続人から暦年課税に係る財産を取得し、その財産について贈与税を支払っていた場合、その被相続人の相続によりその相続人に課せられた相続税額から支払った相続税の金額を控除することができます。これを暦年課税分の贈与税額控除といいます。
相続時精算課税の適用を受けた贈与に係る贈与税額の控除
この制度では、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産に課せられた贈与税について、その財産の受贈者である相続人は、その相続税額から当該贈与税額を控除することができます。当該贈与税額が相続税額よりも大きい場合、当該相続人は贈与税額と相続税額の差額分の還付を受けることができます。
まとめ
ここまで、相続税の税額がどのように決まるのか解説してきました。流れをまとめると次のようになります。
相続発生前の遺言の作成で各相続人への遺産の分配について心配な方は行政書士にご相談ください。
相続発生後の相続税の計算について心配な方は税理士にご依頼ください。
次回の記事では生前贈与にどのようなものがあるか説明します。